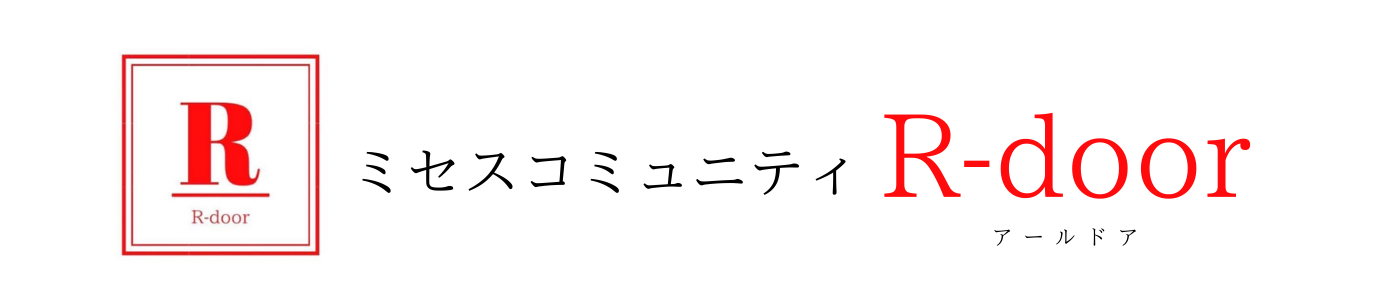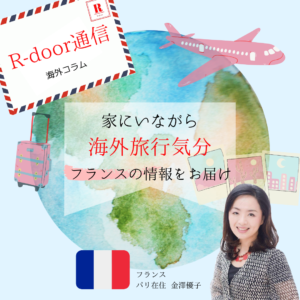9月「着せ綿(きせわた)」歳時記から季節の言葉にふれる
こんにちは。
「お抹茶コミュニケーションSUI」冨田尚子です。

1年にわたりお伝えしてきましたスイーツコラムは、今回が最終回となります。
これまで沢山のあたたかいご声援をいただきこころより感謝申し上げます![]()
![]()
さて。
9月9日は「重陽の節句」でした!
中国では、「一年で最も縁起がよい日」といわれています。
日本では、「菊の節句」とも呼ばれていますね^^
陰陽思想では、奇数は縁起のよい、陽の数。
おめでたい反面、悪いことにも転じやすいと考えられて、
お祝いとともに厄祓いをしてきました。
今回は、日本人のこころの花として古来より親しまれてきた菊をテーマにお届けいたします。
「四君子(しくんし)」とよばれる植物をご存知でしょうか?
古来中国より、
春の蘭、夏の竹、秋の菊、冬の梅は、品格高い植物として、
絵画や図柄に使われています。
菊は、奈良・平安時代に、菊酒を飲む風習とともに中国より伝わりました。
かつて日本には、
野菊のような小さくてかわいらしい花しかなかったそうで、
中国から大輪の花を咲かせる菊が入ってきたときこれが
貴族たちの間で大評判となったそうです!

当時の熱狂ぶりが目に浮かぶようですね。
鎌倉時代になると、天皇家の正式な紋章となりました。
古くから貴族の間では、菊酒や着せ綿の風習があります。
中国にも「菊水伝説」というものがあります。
菊の花からしたたる露が川に落ち、
その川の水を飲んだ者が長寿になったという伝説です。
薬効の植物とされてきた菊が、
語り継がれていまでも不老長寿を願い、邪気を払う花とされています。
そして、日本独自の風習として大切にされてきた
【着せ綿(きせわた)】
これは重陽前夜、
つまり9月8日の晩に女官たちが菊の花に真綿をかぶせて、夜露と香りを移しました。
翌朝、この真綿でからだをなで清めることで、長寿を願いました。
こちらは平安時代から、高貴な人々の間で行われてきました。
「綿」は、木綿、コットンではなく、「絹の真綿(まわた)」を使います。
また、江戸時代なると、
白菊には植物染料で染めた黄色い綿、黄菊には赤い綿、
赤菊には白い綿を被せ、色を変えた綿で蕊(しべ)を作る、
というような細かい決まりもできたそうです。

-肌にあてて清めると、若返り、寿命が千年延びる-
と信じられていて
『紫式部日記』では
「菊の露わかゆばかりに袖ふれて 花のあるじに千代はゆづらむ」
藤原道長の奥方より菊の花を当時、
大変高価であった真綿で覆った菊を贈られた紫式部は
ほんの袖先だけ触れさせて頂き千年の寿命はあなたにお返しします。
という美しい歌を詠みました。
『紫式部日記』以外に、『枕草子』でも着せ綿についての描写があります。
旧暦の時代には盛んに行われていた着せ綿も、新暦が採用されてからは、
9月9日には菊の開花には早く、夜に露も降りません…
そんな理由から明治以降は次第に行われなくなり、
宮中での記録もほとんど残っていないそうです。
※今年の旧暦9月9日は、10月14日
実際の風習は忘れられても、
歳時記から季節の言葉にふれて大切にする和菓子の世界…
受け継がれていく伝統の意匠として伝わるのも改めて、和菓子の魅力だと思っています。
最後に、わたしが個人的におすすめしたい
【大人の雛祭り】
「後の雛(のちのひな)」をご紹介いたします。

これは、9月9日に雛人形と、桃の花の代わりに菊の花を飾り、
大人の女性の長寿、しあわせを願う、主に関西地方で親しまれている習慣です。
以前ホテルロビーで拝見してそれは感動したことを覚えています!!
3月に仕舞った雛人形、内裏雛を、半年後にもう一度飾る風習なのですが…
大切な雛人形を1年間仕舞ったままにせず、虫干しをして痛みを防ぐという習わしです。
長く大切に、という知恵がこめられています。
菊を愛でながら菊酒を愉しみ「大人の雛祭り」
華やかな大人の落ち着きを味わう時間はいかがでしょうか♡
様々な思いがこめられた重陽の節句についてお届けしました。
これからも季節の節目を大切に素敵な時間を重ねてください。
これまでR-doorのコミュニティでの、
コラム執筆活動への応援コラムを介してのご縁にこころより感謝いたします。
またたくさんの応援コメントやいいねをいただき大きな励みとなりました!
この場をお借りしてこころからのお礼と感謝をお伝えさせていただきます♡
そんな溢れる想いをこめて最後のコラムでは
自作の「着せ綿」でふっくらした真綿も表現しました。

コミュニティの皆さまの健やかな日々と、
厄祓いへの想いをこめてこころを込めてつくりました♡涙
おひとりおひとりの輝く日々をこれからも応援しております![]()
![]()
またぜひお会いしましょうね!1年間ありがとうございました。
R-doorオンラインサロンでは、
コラムニストやメンバーの皆さんとの
交流が出来ます。

《プロフィール》
冨田尚子
テーブルで軽やかに豊かに愉しむ茶道
《お抹茶コミュニケーションSUI》代表
国内外のべ1300名以上の方に、テーブル茶道を指導。
日本橋三越本店にて継続講座や、イタリア大使館主催の文化イベントにも登壇。
以前は広告制作やフードコーディネーターとしても活動。
スイーツコラムでは、
美しく美味しいだけではない、
季節にあわせたスイーツの背景やエピソードをご紹介します。
これまでのコラムはこちらから▼
https://rdoor-official.com/category/column/tomitanaoko/
こちらからも世界観をご覧いただけます▼
https://www.reservestock.jp/subscribe/107330/1047407